先月末に行った一般質問の振り返り記事、今回は、議員活動において最も重点を置いている課題の一つ、「義務教育の無償」原則の真の実現に関してご紹介します。
日本国憲法では、第26条で「義務教育は、これを無償とする」と明確に定められています。しかし、実態は、授業料と教科書代のみが無償で、その他の経費は保護者が負担しています。国・社会において「人」が最も大事であり、人を育てる教育は極めて重要です。にもかかわらず、財政的な制約を言い訳にして、憲法制定から今に至るまで、この憲法の「義務教育の無償」原則は実現されないまま、放置されてきました。本当に情けない国だと思います。少子化の一因でもあると捉えています。
私は、子ども・人を大事にして、教育に力を入れる社会・国であるべきと考えるため、この原則の真の実現に取り組んできています。昨年6月の議会から毎回、このテーマを一般質問の項目に盛り込み、教育長及び教育委員会幹部と議論し、議会閉会中も個別協議を継続してきています。
昨年の議会での議論では、教育長から「しっかりと、スピード感をもって取り組む」という旨の表明がありました。そして、教育委員会に「習志野市立学校学習教材検討委員会」が設置されて集中的な検討がなされた結果、学習教材等の共用化を進めて、保護者の経済的負担を軽減する方針が打ち出されました。また、2024年度予算案にも関連予算が盛り込まれました。
このような動きを高く評価し、教育委員会をはじめとする関係者の対応に感謝しつつ、今回の一般質問では、教育委員会での議論を確認しつつ、さらなる予算措置を要望しました。
市内小中学校における副教材費についてはこちらのファイル(27~38頁)で公表されています。このように現状を「見える化」したことも大きな前進ですし、予算措置も、金額は十分ではないですが、実現したことは大きな進展です。
次に必要なことは、動き出した取組の内容・成果・効果をしっかりと検証して、更に予算を増やしていくことです。物価高騰対応等で国から臨時的な交付金が手当てされた場合に、単発の現金給付をするのではなく、効果が複数年度にわたって確保できる教材の共用品化を進めることも提案しました。
憲法の定める「義務教育の無償」原則が真に実現されるその日まで、この課題について全力で取り組んでいきます。そして、保護者の皆様が、経済的負担を心配することなく、小中学校にお子さんを通わせることができる街を目指していきます。
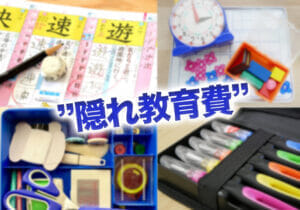
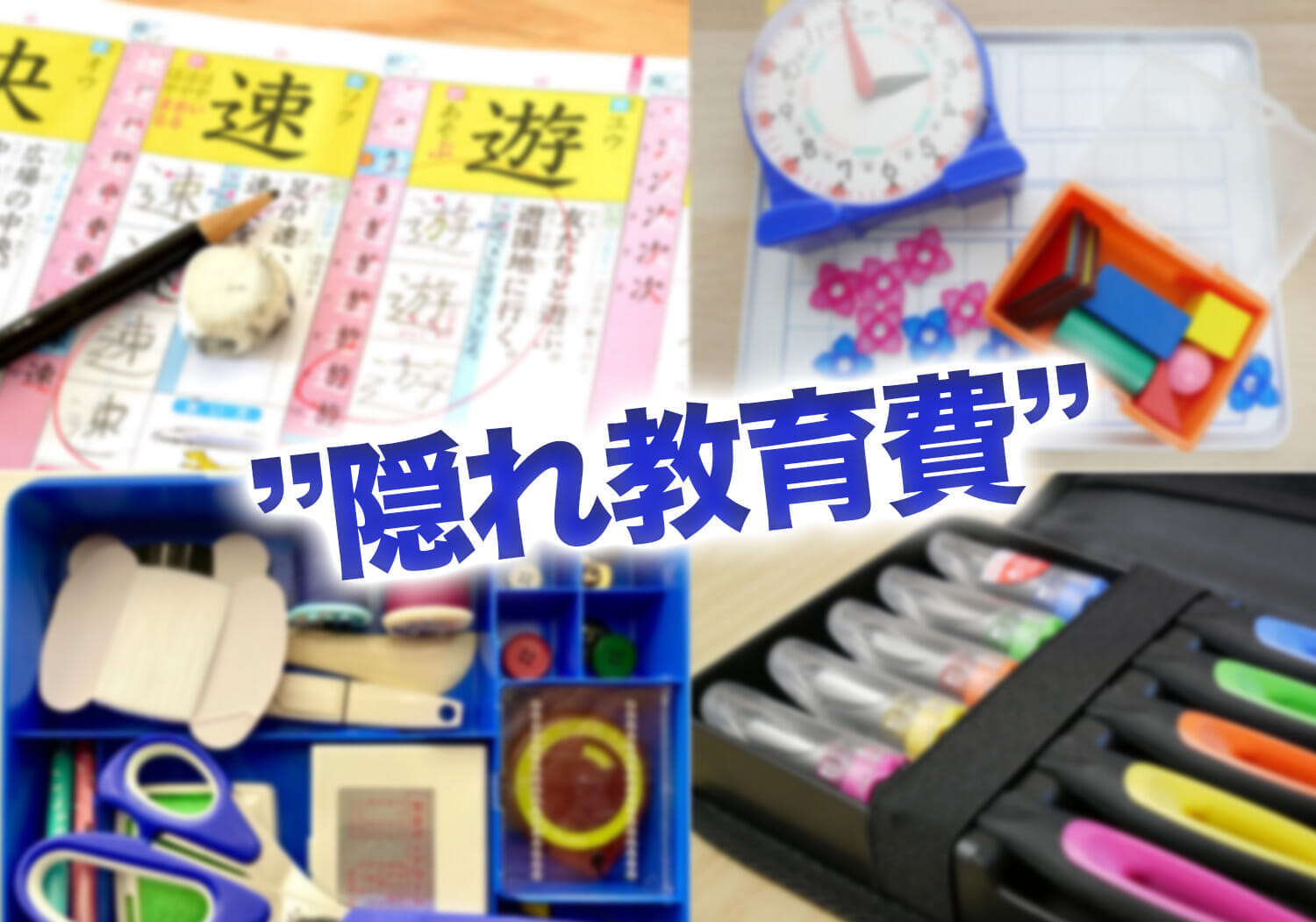


コメント