市議になる前の仕事で、様々な国への駐在や出張を通じて多様な価値観に触れて、また、厳しい現場を体感し、どのような場でも生きていく、仕事をしていく胆力を鍛えてきました(インタビュー記事はこちら)。
この経験の中で「共存」という言葉の意味をずっと考えてきました。世界には異なる宗教や価値観が存在する中で、平和を保ち、そして、紛争を防ぐためには、「共生」ではなく、まず、お互いの存在を認めて存在することを確保する、「共存」が大事です。
価値観が異なるにもかかわらず、仲良く生きることをいきなり目指すのではなく、まずはお互いの存在を知り、尊重し、なんとか同じ社会で暮していくことを目指すべきと考えています。
もちろん、共生、そして、共栄が理想です。でも、理想は理想としつつも、現実はそんなに簡単ではありません。今も世界各地で戦争や紛争が続いている厳しい現実があります。現実を踏まえれば、まずは共存を目指すところから始めるべきです。
外国人の人口が増え始めている日本、習志野市の現状を踏まえても、共存を重視する考え方が大事だと思います。世の中には「多文化共生」という言葉があふれていますが、理想としての共生は大事にしつつ、まずは共存を目指して取り組んでいきます。


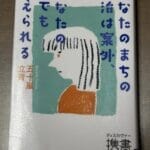
-150x150.jpg)
コメント